

酵母からヒトに至るあらゆる真核生物の細胞内には、膜で囲まれた細胞小器官(オルガネラ)が存在しており、例えば、核(遺伝情報の保持)、ミトコンドリア(エネルギー生産)、ゴルジ体(タンパク質加工)、リソソーム(老廃物処理)等、それぞれのオルガネラが独自の機能を担って細胞の機能を維持しています。細胞が正常に機能するためには、細胞内で合成される膨大な数のタンパク質が各オルガネラへと正確に運ばれる必要があります。また、細胞の中でタンパク質は決してじっとしているわけでなく、オルガネラ間を行き来しながらさまざまな機能を発揮しています。
そのため、オルガネラの多くは小胞輸送とよばれるネットワークによって盛んに物質や情報のやりとりを行っています。小胞輸送とは、送り手側のオルガネラから輸送される生体分子を取り込んだ「輸送小胞」とよばれる直径50〜100ナノメートルほどの小さな膜小胞が出芽し、それが受け手側のオルガネラへと移動し、膜融合によって輸送小胞の中身と膜成分とを受け渡すシステムです。
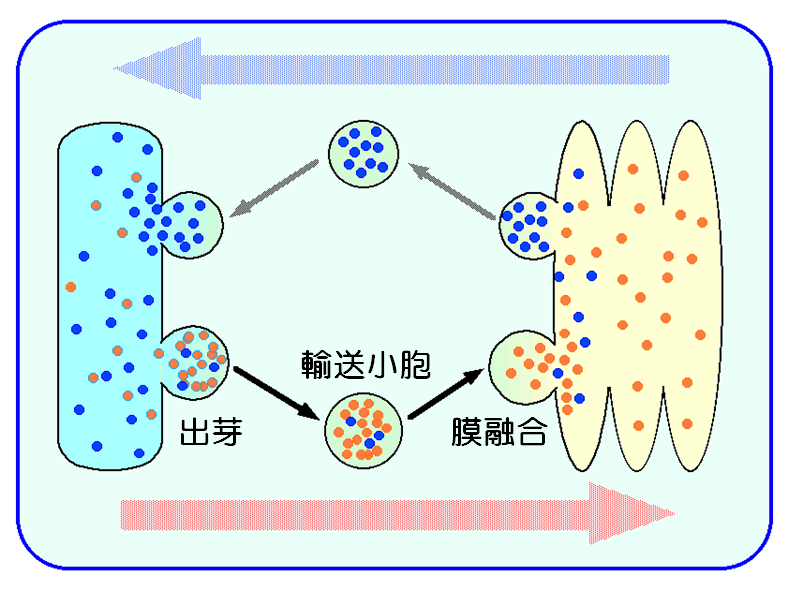
細胞内のオルガネラのうち、小胞体(ER)は各オルガネラの部品となるタンパク質や脂質、あるいは細胞外に分泌されるタンパク質の合成を行っているオルガネラで、細胞内の全タンパク質の約3分の1が小胞体に取り込まれて下流のオルガネラへと移行すると見積もられています。そのため、細胞内の小胞輸送経路のうち、輸送されるタンパク質の種類が最も多いのが小胞体からの小胞輸送であり、さまざまな機能や構造をもったタンパク質が選別を受けて小胞体から形成される輸送小胞に取り込まれて輸送されていきます。

輸送小胞はコートタンパク質とよばれるタンパク質複合体によって被覆されており、それぞれの小胞輸送ルートで異なるコートタンパク質が使われています。小胞体から形成される輸送小胞は、COPIIとよばれるコートタンパク質によって覆われていることから「COPII小胞」とよばれます。
私たちの研究室では、出芽酵母を材料として小胞体からの小胞輸送に焦点を当て、COPII小胞の形成と膜融合のメカニズム、またその過程におけるタンパク質の分子認識と選別のメカニズムを分子レベルで解明することを目指して研究を行っています。
小胞輸送は、細胞の機能のもっとも重要なものの一つです。たとえば、細胞内で作られたタンパク質を細胞外に送り出す「分泌」は小胞輸送のメカニズムで行われています。分泌タンパク質には、細胞外で働くさまざまな酵素群や細胞間相互作用をつかさどるホルモン、リンフォカインなどの重要な分子群が含まれます。また細胞膜の成分である膜タンパク質や、植物や菌類の細胞壁の成分も大部分はこの分泌によって輸送されます。神経におけるシナプス伝達や免疫系における抗原提示は分泌過程そのものです。
小胞輸送の基本的な分子メカニズムは、すべての真核生物において共通であるため、出芽酵母を用いた研究で明らかになるメカニズムは、ヒトなど高等真核生物を含めすべての真核生物に普遍的なものです。また、小胞輸送は他分野にも広く関わる基礎現象であるため、例えばこれまで原因不明であった疾患の原因が小胞輸送機能の損傷にあるものが最近続々と報告されてきています。そのため酵母を用いて小胞輸送のメカニズムを解明することは、現代細胞生物学の重要なテーマであるのみならず、創薬や疾病治療への応用への展開にも大きく寄与するものです。
基礎研究は何のため?
基礎生物学のような基礎研究の目的は「知ること」そのものです。そのため、すぐ目に見える形で技術や産業と結びつくことはありません。しかし、われわれが今日のように繁栄することができたのは、その「知ること」を始めたからだと言われています。目先の利益を性急に求めるばかりでなく、私たちをとりまく世界を、より深く、正確に理解すること。そういう知識によって築かれた基礎をもとにすることで技術も産業も賢く進めて来ることが出来たのです。ただし、技術や産業は目的ではなく手段です。私たちが「知ること」によって繁栄してきたのであれば、これからの私たちが「さらに知ること」によって次のステップへと進んでいけるのかもしれません。さて、みなさんは何を知りたいでしょうか?
教養学部報第506号「時に沿って」”すべては「知ること」から”佐藤健著より抜粋